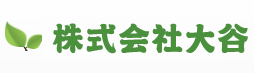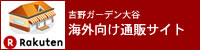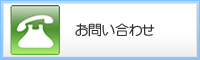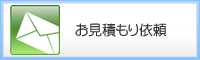|
|
(国宝 蔵王堂) |
|
標高365m吉野山の台地上に立ち並ぶ町並みに大きく抜きん出て、金峯山修験本宗総本山・金峯山寺本堂蔵王堂はそびえたっています。桧皮葺きの重厚な屋根、軽快な反りを見せる軒の出の深さ、それを支える太い柱などを見上げると、まさに国宝建造物蔵王堂は、金峯修験道の根本道場にふさわしい大建築です。 蔵王堂の柱の数は全部で68本。杉・桧・欅・松などの巨大な柱で支えられており、最も太い外陣の「神代杉の柱」といわれる物で周囲が3.6m。ついでそれに向かい合って位置する杉で、3.3mもあり、珍しい材としては、ツツジ・梨などといわれる柱が目を引きます。高い天井を支える列柱群も、内陣の二本の金箔張りの化粧柱を除いては、ほとんど白木のままで用いられ、修験道の生命をかけて修行する、大峯・熊野の厳しい森林の雰囲気をいながらにして感じさせます。 |
|
|
|
(重文 蔵王権現像) |
|
蔵王堂の本尊は、いうまでもなく蔵王権現です。外から見ると蔵王堂はいわば覆屋にすぎません。内陣には高い格天井を突き抜けて、銅板葺きの巨大な厨子があり、その中を三つの間に仕切ったそれぞれに、過去・現在・未来の三世を救済するという、巨大な蔵王権現が三体祭られています。その表情は、荒行にあえていどむ修験者の信仰にふさわしい憤怒の形相に満ちています。 外見は悪魔降伏の恐ろしい姿ですが、その心の中は限りない慈悲を秘めた仏達で、中央尊像は釈迦如来の権現(仮に現れた姿)で過去を救済し、背丈は7.28m。向かって右は現世を救済する千手観音菩薩の権現で6.15m。向かって左は未来を救済する弥勒菩薩の権現で、5.92mもある大きな尊像です。 |
|